和尚のひとりごと№2193「鎌倉法語集」3
和尚のひとりごと№2193「鎌倉法語集」3
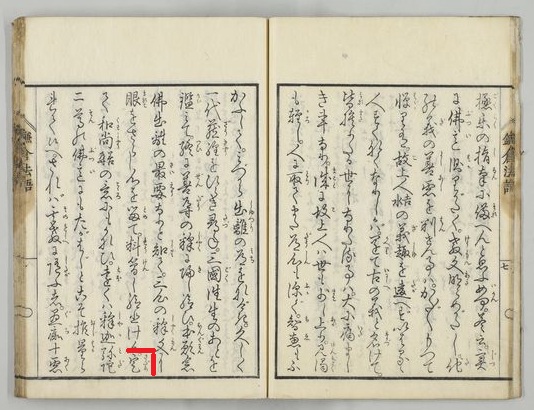
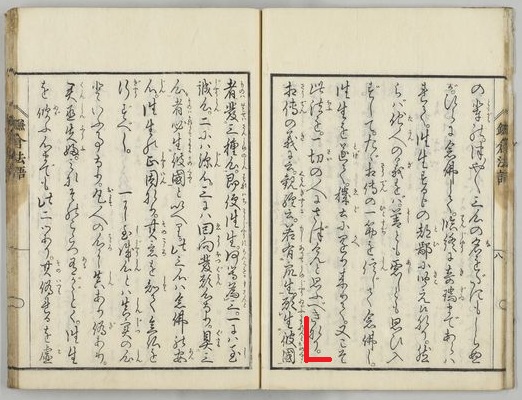
第一:三代の相伝
定(さだ)めて和尚(かしょう)善導(ぜんどう)の意(い)にもかない、遠(とお)くは釈迦(しゃか)弥陀(みだ)二尊(にそん)の仏意(ぶっち)にもたがわじとこそ推(お)し量(はか)られてそうらえ、さればその教(おし)えに随(したが)う者(もの)、愚癡(ぐち)十悪(じゅうあく)の輩(やから)のつやつや三心(さんじん)の名(な)をだにもしらぬが、ひらに念仏(ねんぶつ)して臨終(りんじゅう)に奇瑞(きずい)まであらわれて、往生(おうじょう)するもの都鄙(とひ)に聞(きこ)えそうろうなり。然(しか)らば他人(たにん)の義(ぎ)をば、善(よ)しとも悪(あ)しとも思(おも)い入(いれ)ずしてただ相伝(そうでん)の一筋(ひとすじ)を信(しん)じて念仏(ねんぶつ)し、往生(おうじょう)を遂(と)げて穢土(えど)に還(かえ)り来(き)たりて、またこそこの法(ほう)を一切(いっさい)の人(ひと)にさずけんと思(おも)うべきなり。
【浄土行者用意問答 浄全一〇 七〇〇上】

良忠上人(光明寺蔵)
【訳】
上人は、それは間違いなく善導大師の御心に適うものであり、遠くは釈尊と阿弥陀仏の二尊の御仏の心にも異ならないものであろうと推測されたのです。それゆえ、その教えに従う者は愚癡の身であり、仏教の掟に背いて十悪を犯し、三心の名前さえも全く知らないとしても、ひたすら念仏を称えることで臨終の時には往生を示す不思議な出来事が起こり、確かに往生したという評判が都にも地方にも立っています。ですから、他人の主張することについては善し悪しを論ぜず、ただ一筋に相伝された教えを信じて念仏を称えて往生を遂げ、その後、穢れの多いこの世界に帰ってきて、再びその時にこの念仏の教えをすべての人に教え示そうと思うべきなのです。
奇瑞(きずい)
不思議な出来事のこと、またよいことが起こる前兆。奇瑞は、偉大な宗教者の節目となるような体験の前後に現れることが多い。そのような奇瑞を体験した人々は、それぞれ信仰を確固たるものとし、奇瑞を起こした宗教者を仰ぐようになる。『四十八巻伝』には、法然の誕生時に二流ふたながれの白幡が飛んできて庭の椋の木に掛かったこと(巻一)や、往生の前後に多くの人々が不思議な体験をしたこと(巻三七)などが説かれている。法然の伝記には、このほかにも多くの奇瑞が説かれ、法然の周囲の人々はそのような体験を通して法然自身への帰依を深め、念仏往生への信仰を確固たるものにしたと考えられる。(浄土宗大辞典)
※大本山光明寺さまより発行されている『鎌倉法語集 良忠上人のお言葉』より再掲引用させていただいた内容となります。
